家族信託ってなに?後見制度を使わずに財産管理する方法とは
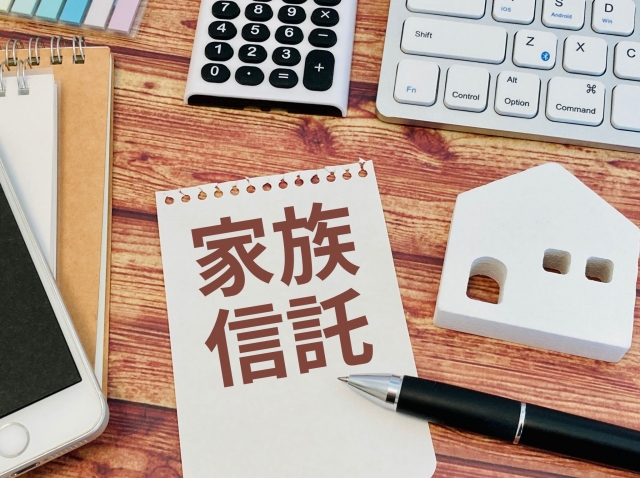
家族信託という制度を聞いたことはありますでしょうか。
「家族信託」と聞くと、難しい制度のように思う方もいらっしゃるかもしれません。
家族信託とは、文字通り「家族」で財産管理を「信」じて「託」す仕組みのことです。
家族信託はいろんな場面で使用できますが、最も一般的な使い方は親の認知症対策です。
もし、何も対策をしていない状態で親が認知症になってしまった場合、子どもであれど親の財産を自由に使用したり、運用したりすることはできなくなってしまいます。
親御さん自身では手続きや契約行為などができない状態ですので、生活に支障があるのはいうまでもありません。
そんな時に、役立つのが家族信託です。
特に、どのような場面で家族信託が有効なのかもあわせて、お伝えしていきたいと思います。
今回の記事は、以下のような人におすすめです。
・持ち家を所有している高齢の親がいる方
・将来、親の家の売却をする可能性がある方
・財産管理ではできるだけ後見制度を使いたくない方
ぜひ最後までご覧ください。
【目次】
・家族信託とは
・家族信託の活用例
・家族信託の有用性
・まとめ
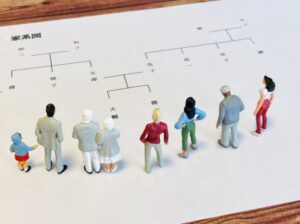
「家族信託」とは、一言でいうと『財産管理の一手法』です。
引用:一般社団法人 家族信託普及協会ホームページより
家族信託とは、財産を持つ人(委託者)が信頼できる家族など(受託者)に財産の管理・運用・処分を託し、その利益を特定の人(受益者)が受け取る仕組みです。
認知症対策や相続対策として注目されており、本人の判断能力が低下してもスムーズな財産管理が可能になるのが特徴です。
管理を託すのは、元から信頼関係のある家族・親族になるケースが多いです。
財産管理にあたって、高額な報酬を支払う必要はありません。
またこの制度は、資産がたくさんある人だけのものではなく、誰にでも気軽に利用できる仕組みになっていますので、家族の中で財産管理したい方には、有効な制度です。
家族信託で主な登場人物は下記の3者になります。
①委託者(財産管理を依頼する人)=親
②受託者(財産管理を受ける人)=子
③受益者(預けた財産からの収益を得る人)=親
家族信託では、財産管理を依頼するのは親になります。
子どもは、親の財産管理を引き受けるので、受託者です。
親は、子どもに財産管理を依頼しますが、財産自体は親の物。
決して子に財産をあげたわけではない点がポイントです。
ですから財産の収益を得る人は、親のままです。
イメージは、親が子どもに自分の財布を渡し、子どもに管理してと頼むような感じです。
仮に親が認知症になってしまって、自分の財産管理ができない状態になっても、
子どもと信託契約をしておけば、親の財産管理がスムーズにできるのです。
子どもが管理するとはいっても、あくまで受益者は親です。
そのため、子どもは預かった財産を自分のために使ってはなりません。
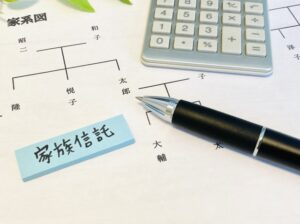
家族信託は具体的にどのような場面で使われるのか、よくあるケースを紹介します。
【家族構成】
・A子さん
・A子さんの兄
・A子さんの母親
※A子さんの父親は既に他界
A子さんの母親が80歳になりました。
父親はすでに他界しているため、実家には母親が一人暮らしでした。
実家は築年数が経過して老朽化をしていたのと、高齢になった母親にとっては大きすぎる家だったので、そろそろ実家を売却して、介護施設に入ろうかと検討していました。
元気なうちにちょうど良さそうな介護施設を見つけることができ、その介護施設に入所をすることになりました。
まだその段階では母親は元気で、身の回りのことも自分でできる状態だったので、老朽化した実家は手放さず、時々、介護施設から実家に帰ったりしていました。
ちなみにA子さんとお兄さんは、2人とも既に結婚をしていて、子どもがおり、それぞれ持ち家をもっていました。
将来的に母親が他界してどちらかが実家を相続することになったとしても、2人とも今のところ実家には住む予定はありません。
ですからいずれは、実家を売却することになるはずです。
この段階では、まだ誰も困ることはありません。
このようなケースの方は、大勢いらっしゃるでしょう。
さて本題はここからです。
このような状況下で母親が認知症になってしまった場合、どうなるのでしょうか。
母親が認知症になって、「判断能力」が低下すると、法律上の契約行為ができなくなり、銀行口座の管理や不動産の売却などが本人ではできなくなります。
例えば、親名義の実家を売却して、親が入所している介護施設の利用料や生活費に充てようとしても、
親が認知症を発症していると「売却契約を理解し同意する能力」がないと判断され、売買契約そのものが無効になります。
この場合、家庭裁判所に「成年後見制度」の申立てを行い、後見人に実家の売却をしてもらう必要がありますが、後見制度は手続きが煩雑で、家族が自由な財産管理をしずらくなるデメリットがあります。
こうした事態を防ぐために、家族信託があります。
家族信託を締結しておくと、後見制度を利用せずに、家族(受託者)の裁量だけで実家を売却するなどの手続きが可能になるのです。

実家が古くなり、親が住まなくなったら売却するしかない状態・・・となっても、実家には家族の思い出がたくさん詰まっています。
親御さんが「自分が元気なうちは家は売りたくない」と思われるのも当然です。
しかし、その一方で「もし自分が認知症になって家に住めなくなった場合、家を売却して、子どもたちに迷惑がかからないようにしたい」という想いがある方もいらっしゃるでしょう。
また自分が財産の管理ができなくなった時は、子どもに全てを任せたい、という想いもあるかもしれません。
そのような場合は、家族信託を締結しておくと、想いを叶えることができます。
家族信託は、親の代わりに家の売却の手続きができる、というのはもちろんですが、売却だけではなく、保有したまま有効活用するという観点でも便利な制度です。
例えば、不要になった実家が都心にあって賃貸需要が見込めるようであれば、リフォームをして賃貸する方法もあります。
親の財産を子どもが管理できるようにしておけば、親のお金で家をリフォームすることで、相続税の圧縮にも効果があります。
また賃貸での活用をすれば、土地の相続税評価額も下がるうえ、家賃収入も入ることになります。
入ってきた家賃収入は、親御さんの生活費や介護費にも活用できるでしょう。
また将来、親の実家を相続して子どもが住む場合には、親が元気なうちに親の資金で実家を建て替えておく方法もあります。
一旦、実家を売却して現金化するのも良いですし、家を売ったお金で収益物件に買替えをした場合でも相続税対策になります。
後見制度では、ここまでのことはできません。
このように家族信託をしておくことで、親が認知症になった後でも、子どもの権限で親の財産管理・運用ができるようになるので大変便利なのです。
また家族信託は、家族の状況に合わせた適切な仕組みにしておくことも可能です。
例えば、兄妹2人が相続人の場合には、長男を受託者にし、長女を信託監督人としてつけておくこともできます。
そうすると、財産管理をする際、長男だけの判断ではなく、長女の意見も聞き、承諾を得たうえで家の売却などの重要な行為を実行する流れになります。
さらに家族信託では遺言的な機能を持たすこともできますので、将来、財産を残したい相手を決めておくこともできます。
家族信託を検討することによって、おのずと家族の中で「将来親に何かあった時、誰がどのように財産管理をするか。誰が親の面倒をみるのか」を話し合う機会を持つことができます。
家族間で、親の介護や相続に関して話せる機会を持つのは、当たり前のようでなかなか難しいものです。
家族信託の検討をきっかけにして、将来のことを親・兄弟・相続人同士で考え、話し合うことができるという意味でも、大変意義深い制度だと思います。
今回は、高齢の親がいらっしゃる方で、将来、実家を相続する可能性がある方に向けて、家族信託についてご紹介しました。
将来の親の財産管理や相続のことについては、まずは家族で話をしてみることがスタートラインです。
とはいえ、自分の家族ではどのような方法をとるべきか、適切な専門家をどのように探していけばよいのかなど、相続に関する疑問は尽きないですよね。
不動産相続アーキテクツの無料相談では、相続や家族信託に関するご相談、必要な専門家への相談のご紹介をしています。
どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
「家族信託」と聞くと、難しい制度のように思う方もいらっしゃるかもしれません。
家族信託とは、文字通り「家族」で財産管理を「信」じて「託」す仕組みのことです。
家族信託はいろんな場面で使用できますが、最も一般的な使い方は親の認知症対策です。
もし、何も対策をしていない状態で親が認知症になってしまった場合、子どもであれど親の財産を自由に使用したり、運用したりすることはできなくなってしまいます。
親御さん自身では手続きや契約行為などができない状態ですので、生活に支障があるのはいうまでもありません。
そんな時に、役立つのが家族信託です。
特に、どのような場面で家族信託が有効なのかもあわせて、お伝えしていきたいと思います。
今回の記事は、以下のような人におすすめです。
・持ち家を所有している高齢の親がいる方
・将来、親の家の売却をする可能性がある方
・財産管理ではできるだけ後見制度を使いたくない方
ぜひ最後までご覧ください。
【目次】
・家族信託とは
・家族信託の活用例
・家族信託の有用性
・まとめ
家族信託とは
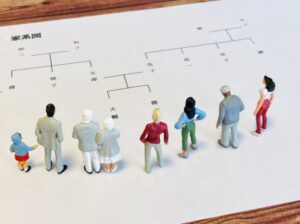
家族信託とはどのような制度でしょうか
「家族信託」とは、一言でいうと『財産管理の一手法』です。
引用:一般社団法人 家族信託普及協会ホームページより
家族信託とは、財産を持つ人(委託者)が信頼できる家族など(受託者)に財産の管理・運用・処分を託し、その利益を特定の人(受益者)が受け取る仕組みです。
認知症対策や相続対策として注目されており、本人の判断能力が低下してもスムーズな財産管理が可能になるのが特徴です。
管理を託すのは、元から信頼関係のある家族・親族になるケースが多いです。
財産管理にあたって、高額な報酬を支払う必要はありません。
またこの制度は、資産がたくさんある人だけのものではなく、誰にでも気軽に利用できる仕組みになっていますので、家族の中で財産管理したい方には、有効な制度です。
家族信託で主な登場人物は下記の3者になります。
①委託者(財産管理を依頼する人)=親
②受託者(財産管理を受ける人)=子
③受益者(預けた財産からの収益を得る人)=親
家族信託では、財産管理を依頼するのは親になります。
子どもは、親の財産管理を引き受けるので、受託者です。
親は、子どもに財産管理を依頼しますが、財産自体は親の物。
決して子に財産をあげたわけではない点がポイントです。
ですから財産の収益を得る人は、親のままです。
イメージは、親が子どもに自分の財布を渡し、子どもに管理してと頼むような感じです。
仮に親が認知症になってしまって、自分の財産管理ができない状態になっても、
子どもと信託契約をしておけば、親の財産管理がスムーズにできるのです。
子どもが管理するとはいっても、あくまで受益者は親です。
そのため、子どもは預かった財産を自分のために使ってはなりません。
家族信託の活用例
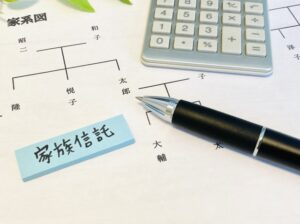
家族信託の活用例を紹介します
家族信託は具体的にどのような場面で使われるのか、よくあるケースを紹介します。
【家族構成】
・A子さん
・A子さんの兄
・A子さんの母親
※A子さんの父親は既に他界
A子さんの母親が80歳になりました。
父親はすでに他界しているため、実家には母親が一人暮らしでした。
実家は築年数が経過して老朽化をしていたのと、高齢になった母親にとっては大きすぎる家だったので、そろそろ実家を売却して、介護施設に入ろうかと検討していました。
元気なうちにちょうど良さそうな介護施設を見つけることができ、その介護施設に入所をすることになりました。
まだその段階では母親は元気で、身の回りのことも自分でできる状態だったので、老朽化した実家は手放さず、時々、介護施設から実家に帰ったりしていました。
ちなみにA子さんとお兄さんは、2人とも既に結婚をしていて、子どもがおり、それぞれ持ち家をもっていました。
将来的に母親が他界してどちらかが実家を相続することになったとしても、2人とも今のところ実家には住む予定はありません。
ですからいずれは、実家を売却することになるはずです。
この段階では、まだ誰も困ることはありません。
このようなケースの方は、大勢いらっしゃるでしょう。
さて本題はここからです。
このような状況下で母親が認知症になってしまった場合、どうなるのでしょうか。
母親が認知症になって、「判断能力」が低下すると、法律上の契約行為ができなくなり、銀行口座の管理や不動産の売却などが本人ではできなくなります。
例えば、親名義の実家を売却して、親が入所している介護施設の利用料や生活費に充てようとしても、
親が認知症を発症していると「売却契約を理解し同意する能力」がないと判断され、売買契約そのものが無効になります。
この場合、家庭裁判所に「成年後見制度」の申立てを行い、後見人に実家の売却をしてもらう必要がありますが、後見制度は手続きが煩雑で、家族が自由な財産管理をしずらくなるデメリットがあります。
こうした事態を防ぐために、家族信託があります。
家族信託を締結しておくと、後見制度を利用せずに、家族(受託者)の裁量だけで実家を売却するなどの手続きが可能になるのです。
家族信託の有用性

家族信託は何に役立つでしょうか
実家が古くなり、親が住まなくなったら売却するしかない状態・・・となっても、実家には家族の思い出がたくさん詰まっています。
親御さんが「自分が元気なうちは家は売りたくない」と思われるのも当然です。
しかし、その一方で「もし自分が認知症になって家に住めなくなった場合、家を売却して、子どもたちに迷惑がかからないようにしたい」という想いがある方もいらっしゃるでしょう。
また自分が財産の管理ができなくなった時は、子どもに全てを任せたい、という想いもあるかもしれません。
そのような場合は、家族信託を締結しておくと、想いを叶えることができます。
家族信託は、親の代わりに家の売却の手続きができる、というのはもちろんですが、売却だけではなく、保有したまま有効活用するという観点でも便利な制度です。
例えば、不要になった実家が都心にあって賃貸需要が見込めるようであれば、リフォームをして賃貸する方法もあります。
親の財産を子どもが管理できるようにしておけば、親のお金で家をリフォームすることで、相続税の圧縮にも効果があります。
また賃貸での活用をすれば、土地の相続税評価額も下がるうえ、家賃収入も入ることになります。
入ってきた家賃収入は、親御さんの生活費や介護費にも活用できるでしょう。
また将来、親の実家を相続して子どもが住む場合には、親が元気なうちに親の資金で実家を建て替えておく方法もあります。
一旦、実家を売却して現金化するのも良いですし、家を売ったお金で収益物件に買替えをした場合でも相続税対策になります。
後見制度では、ここまでのことはできません。
このように家族信託をしておくことで、親が認知症になった後でも、子どもの権限で親の財産管理・運用ができるようになるので大変便利なのです。
また家族信託は、家族の状況に合わせた適切な仕組みにしておくことも可能です。
例えば、兄妹2人が相続人の場合には、長男を受託者にし、長女を信託監督人としてつけておくこともできます。
そうすると、財産管理をする際、長男だけの判断ではなく、長女の意見も聞き、承諾を得たうえで家の売却などの重要な行為を実行する流れになります。
さらに家族信託では遺言的な機能を持たすこともできますので、将来、財産を残したい相手を決めておくこともできます。
家族信託を検討することによって、おのずと家族の中で「将来親に何かあった時、誰がどのように財産管理をするか。誰が親の面倒をみるのか」を話し合う機会を持つことができます。
家族間で、親の介護や相続に関して話せる機会を持つのは、当たり前のようでなかなか難しいものです。
家族信託の検討をきっかけにして、将来のことを親・兄弟・相続人同士で考え、話し合うことができるという意味でも、大変意義深い制度だと思います。
まとめ
今回は、高齢の親がいらっしゃる方で、将来、実家を相続する可能性がある方に向けて、家族信託についてご紹介しました。
将来の親の財産管理や相続のことについては、まずは家族で話をしてみることがスタートラインです。
とはいえ、自分の家族ではどのような方法をとるべきか、適切な専門家をどのように探していけばよいのかなど、相続に関する疑問は尽きないですよね。
不動産相続アーキテクツの無料相談では、相続や家族信託に関するご相談、必要な専門家への相談のご紹介をしています。
どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
SHARE
シェアする
[addtoany] シェアする

