豊島区での兄弟姉妹との相続トラブル対策
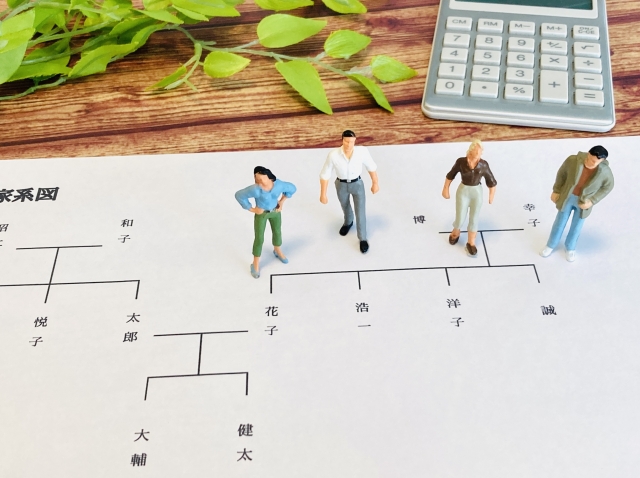
【導入】 「兄とは絶対に揉めたくない」「妹とは普段仲がいいけれど、相続となると心配」——そんな不安を抱える人は少なくありません。
実際、相続トラブルの大半は「お金持ちの家庭」ではなく、むしろ一般家庭で兄弟姉妹間に生じるといわれています。特に豊島区のように地価が高く、不動産が相続財産の中心になるエリアでは、遺産分割が難航しやすく、関係が悪化する事例も多く見られます。
この記事では、豊島区における兄弟姉妹との相続トラブルを未然に防ぐ方法や、実際に起きたケースとその対応策について、実務に基づいてわかりやすく解説します。
【第1章】兄弟姉妹間でトラブルが起きやすい理由
■ 財産の中心が「不動産」
・分けづらい・売りづらい・評価が人によって違う
・特に豊島区では単価が高く、少しの差が大きな不満に
■ 親の介護負担に対する不満
・長男だけが介護していた、遠方の妹は何もしていない…など
・感情的な軋轢が分割協議に持ち込まれやすい
■ 遺言書がない/内容が曖昧
・法定相続分で分けられないことが多く、争いに発展
■ 家族間のコミュニケーション不足
・相続の話を避ける家庭が多い
・親が亡くなってから初めて本音をぶつける場に
【第2章】豊島区で実際に起きたトラブル事例
■ ケース1:古い実家の相続でもめた兄弟
・目白の築40年の木造戸建てが遺産
・長男はそのまま住みたい、弟は売却して現金で分けたい
・不動産の評価額に大きな認識差があり、協議が平行線
■ ケース2:介護を担っていた姉が多めに欲しいと主張
・母の介護を担った長女が「その分多くもらうのは当然」と主張
・弟たちは「感謝はするが、法定通りに分けるべき」と反発
■ ケース3:遺言書があったが曖昧な記載で混乱
・「○○に実家を任せる」と書かれていたが、具体的な相続内容が明記されておらず対立
【第3章】兄弟姉妹間トラブルを防ぐための対策
■ 1. 親が元気なうちに家族会議を開く
・財産の概要や意向を共有
・介護・医療・葬儀の負担分担についても話し合う
■ 2. 遺言書を活用する(できれば公正証書で)
・財産の分け方を明確に指定
・付言事項で感謝や理由を書くと納得感が高まる
■ 3. 生前贈与や家族信託の活用
・争族回避のため、計画的に財産を動かす
・認知症になる前に対策を講じる
■ 4. 第三者の専門家に依頼する
・弁護士、司法書士、税理士が中立的立場で調整
・感情的対立を防止できる
■ 5. 評価の異なる不動産には慎重対応
・分筆や共有解消、換価分割(売却して現金化)なども検討
【第4章】相続発生後にトラブルが起きた場合の対応策
■ 話し合い(遺産分割協議)を試みる
・まずは冷静な協議を心がける
・メールやLINEなど記録が残る手段を使うのも有効
■ 第三者に調停や仲裁を依頼
・家庭裁判所の遺産分割調停を利用
・豊島区の弁護士会の無料相談を活用するのも一案
■ 司法手続きに発展する前に専門家を交える
・相続関係説明図や財産目録をプロに作成依頼
・書類の整理でスムーズな協議が可能に
【第5章】まとめ:家族の絆を守るために
豊島区に限らず、兄弟姉妹間の相続トラブルは全国的に多発しています。特に、不動産が遺産の大部分を占める場合、感情や立場の違いが顕在化しやすくなります。
親が元気なうちから「何を残すか」「どう分けるか」を家族で話し合い、信頼できる専門家を交えた備えをすることで、大切な家族関係を守ることができます。
トラブルを防ぐ最大の武器は「準備と対話」です。豊島区にお住まいの方も、ぜひ今日から相続対策を始めてみてください。
SHARE
シェアする
[addtoany] シェアする

