豊島区で自宅の評価を抑える「小規模宅地の特例」活用例
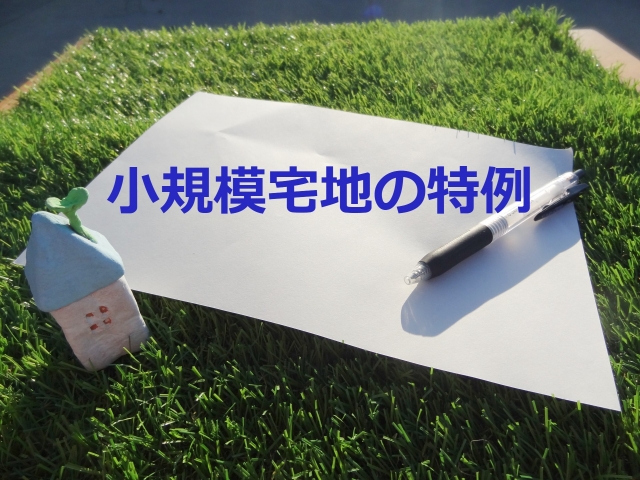
相続税対策として非常に効果的とされる「小規模宅地等の特例」。特に不動産価格の高い豊島区では、この特例を適用できるか否かで納税額が大きく変わる可能性があります。
「うちは対象になるのか?」「どれくらい税金が減るのか?」と疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
この記事では、豊島区で自宅を相続する際にこの特例を上手に活用する具体的な方法や条件、注意点について、詳しく解説します。
【第1章】小規模宅地等の特例とは?
■ 制度の概要
・相続した宅地のうち、一定の要件を満たすものについて最大80%まで評価額を減額できる制度
・被相続人の居住用、事業用、貸付用の宅地が対象
■ 豊島区での影響
・地価が高いため、評価減のインパクトが非常に大きい
・例:評価額1億円の宅地が2,000万円に減額されることも
【第2章】居住用宅地における適用条件
■ 条件の要点
・被相続人が死亡時に住んでいた宅地であること
・配偶者、または同居していた親族が相続し、その後も住み続けること
■ 特例の内容
・最大330㎡まで、評価額の80%が減額される
・評価額が1億円であれば2,000万円まで減額可能
■ 豊島区での活用例
・目白にある敷地200㎡の戸建住宅を長男が同居相続
・通常評価:1㎡あたり130万円 → 総評価額2.6億円
・特例適用後:2.6億円 × 20%=5,200万円に評価減
【第3章】具体的な活用事例(豊島区編)
■ 事例1:配偶者が相続するケース
・被相続人:80代男性、豊島区南池袋の持ち家に妻と同居
・相続人:配偶者と子供2人
・結果:妻が自宅を相続 → 小規模宅地の特例で80%減額 → 相続税ゼロに
■ 事例2:子供が同居していたケース
・被相続人:一人暮らしの母親、長男と同居
・長男が相続し住み続ける → 特例適用OK
・評価額7,000万円 → 1,400万円に
■ 事例3:二世帯住宅の一方が被相続人
・同一建物内で親と子が完全分離して生活していた場合でも、要件を満たせば特例適用可
・登記上の分離状況や居住実態がカギとなる
【第4章】注意点と適用できないケース
■ 単身者が亡くなり、別居の子が相続する場合
・原則適用できない
・生計一親族や家なき子特例などの別条件が必要
■ 相続後すぐに売却した場合
・居住要件が満たされず、特例が否認されることがある
■ 名義だけの同居はNG
・実態としての同居が確認される必要あり
・住民票やライフライン契約で裏付けが必要
■ 豊島区特有の留意点
・宅地の面積が狭小な場合でも、評価額が高くなることが多い
・路線価の高い地域では、小さな宅地でも減額効果が大きい
【第5章】適用のための実務と専門家の関与
■ 必要な書類
・戸籍謄本、住民票、固定資産税評価証明書、遺産分割協議書など
・登記簿謄本で所有状況を確認
■ 専門家に依頼するメリット
・税理士:適用条件の判断、申告書類の作成
・司法書士:名義変更、遺言執行
・不動産鑑定士:評価額の適正化
■ 豊島区での実務例
・不動産に強い税理士事務所との連携で、早期の評価減対策
・区役所や税務署への相談も並行して行う
【まとめ】特例を活用して負担を軽減
豊島区のように地価が高い地域では、小規模宅地等の特例を使うか使わないかで相続税額に大きな差が出ます。要件をしっかり確認し、早めに専門家と連携することで、安心して相続手続きを進めることができます。
「自宅を引き継ぎたいけど、税金が心配」という方は、ぜひこの制度の活用を前提に相続の準備を始めてみてください。
SHARE
シェアする
[addtoany] シェアする

