豊島区での家族信託を活用した不動産管理術
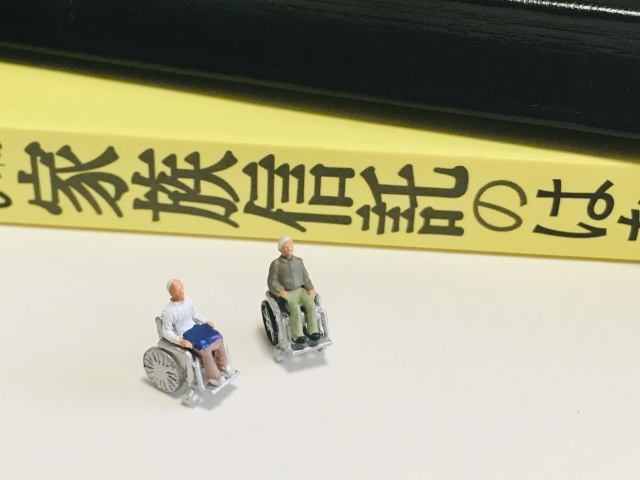
近年、「家族信託」という仕組みが注目を集めています。特に不動産を所有するご家庭では、認知症対策や円滑な相続、不動産の有効活用のために導入するケースが増えてきました。
豊島区は都心部に位置し、地価が高く、不動産を所有するだけで相続や税金の課題が大きくなりがちなエリアです。そのため、「相続対策」と「不動産管理」の両方を実現する方法として、家族信託は非常に有効です。
本記事では、豊島区で不動産を所有する方に向けて、「家族信託を活用した不動産管理術」を解説します。
第1章:家族信託とは?
1.1 基本的な仕組み
家族信託とは、財産を持つ「委託者」が、信頼できる家族(「受託者」)に不動産などの財産を託し、その管理や運用を任せる制度です。財産の利益は、最終的に「受益者」が享受します。
例:
委託者(親) → 不動産を託す
受託者(子) → 不動産を管理する
受益者(親) → 家賃収入を得る
1.2 遺言や成年後見との違い
遺言:効力は死亡後のみ
成年後見:裁判所が監督し、柔軟な運用が難しい
家族信託:生前から効力を発揮し、自由度の高い財産管理が可能
第2章:豊島区で家族信託が注目される理由
2.1 高額な不動産価値
豊島区の不動産は、池袋や目白といった一等地では数億円規模に達することもあります。高額資産を相続する際には、相続人間でのトラブルや納税資金不足が起こりやすいため、事前の仕組みづくりが欠かせません。
2.2 認知症リスクへの対応
不動産オーナーが認知症になると、売却・賃貸契約・担保設定などの法律行為ができなくなります。家族信託を設定しておけば、受託者である子どもが代わりに手続きを行えるため、資産凍結を防げます。
2.3 相続トラブル防止
遺言書だけでは不動産の共有状態が発生しやすく、兄弟姉妹間の揉め事につながります。家族信託なら、誰が管理し利益を受けるかを明確にでき、分割トラブルを回避できます。
第3章:家族信託の具体的な活用例(豊島区の不動産)
3.1 賃貸アパート経営の継続
・親が高齢化しても、子が受託者となり契約更新や修繕を行える
・家賃収入は親(受益者)が受け取り、生活費に充当可能
3.2 売却や建替えの柔軟化
・老朽化した木造アパートを売却 → 信託契約に基づき子が代理で契約可能
・タワーマンション用地としてデベロッパーに売却 → 手続きがスムーズに進む
3.3 相続税対策
・生前から財産の承継順序を決められる
・「二次相続」まで指定でき、相続税の負担分散につながる
3.4 空き家問題への対応
・相続後に活用方針が決まらず放置 → 家族信託で受託者に「売却」「賃貸化」の権限を与え、迅速に動ける
第4章:家族信託の手続きの流れ
1.専門家へ相談(司法書士・弁護士・税理士など)
2.信託設計(財産の範囲、受託者、受益者、終了条件などを決定)
3.信託契約書の作成(公正証書化が望ましい)
4.登記申請(不動産を信託財産として登記する)
5.運用開始(受託者が管理・契約を実施)
第5章:注意点とデメリット
・受託者に大きな権限が集中するため、信頼できる人物を選ぶ必要がある
・信託契約の内容が複雑で、専門家の関与が不可欠
・登記費用や専門家報酬が発生する
・銀行融資や売却時に「信託登記」が敬遠される場合がある
第6章:事例紹介(豊島区)
事例1:池袋の一棟マンション
80代男性が所有していた一棟マンションを、長男を受託者にして家族信託化。認知症発症後も長男が賃貸契約更新・修繕を実施し、安定収入を確保。相続発生時もスムーズに承継。
事例2:巣鴨の古家付き土地
相続後に空き家となる可能性が高い土地を、家族信託で次男に管理権限を付与。相続発生後すぐに売却し、相続税納税資金を確保。兄弟間トラブルを防止。
まとめ
豊島区で不動産を相続・管理する際、家族信託は「認知症リスクへの備え」「相続トラブルの回避」「資産活用の柔軟化」という3つの大きなメリットをもたらします。
ただし、制度設計や運用には専門的な知識が必要であり、信頼できる専門家との連携が成功のカギです。
相続を「争族」にしないために、また大切な不動産を有効活用するために、家族信託という選択肢を早めに検討してみてはいかがでしょうか。
シェアする

